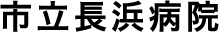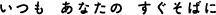泌尿器科
ご案内 スタッフ紹介 外来担当医表 学会・論文発表 診療トピックス
ご案内
| ■診療内容 | 2023年4月より、常勤医師2名と非常勤医師2名による診療体制となります。可能な限り泌尿器科救急処置や必要な手術は迅速に行うようにし、湖北圏域をはじめとした近隣の泌尿器科診療施設と協力しながら、受診される患者さんが最も良い治療を選択できるように努めます。 泌尿器科では、尿路および男性性器の腫瘍(癌)、尿路結石、排尿障害の治療を主に行っています。悪性腫瘍に対しては可能な限り迅速に対応して必要な検査を行い、手術・化学療法・放射線治療を主として集学的治療を行います。必要時は近隣病院や大学病院などへの橋渡しを行います。結石や排尿障害などの良性疾患に対しては可能な治療法を提示し、相談のうえで治療方針を決めていきます。 |
|---|---|
| ■施設認定 | 日本泌尿器科学会専門医基幹教育施設 |
スタッフ紹介
| 役職等 | 名前 | 資格 |
|---|---|---|
| 責任部長 | 村井 亮介 | 日本泌尿器科学会専門医 日本泌尿器科学会指導医 日本がん治療認定機構 がん治療認定医 日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医 |
| 医長 | 山内 直也 | 日本泌尿器科学会 |
| 担当医師 (非常勤) |
村元 暁文 | |
| 担当医師 (非常勤) |
奥村 勇太 |
外来担当医表
外来担当医については、下記リンクをご参照ください。
休診、代診のお知らせについては、下記リンクをご参照ください。
学会・論文発表
学会・論文発表につきましては、下記リンクをご参照ください。
診療トピックス
▶主な手術・検査件数
(単位:件数)
| 手術名・検査名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 |
| 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術 | 9 | 5 | 4 |
| 腹腔鏡下副腎摘出術 | 1 | 2 | 1 |
| 根治的膀胱全摘除術 | 0 | 2 | - |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) | 45 | 40 | 30 |
| 経尿道的腎尿管結石砕石術(TUL) | 59 | 45 | 31 |
| 経尿道的膀胱結石砕石術 | 6 | 8 | 5 |
| 経尿道的前立腺切除術(TURP) | 21 | 12 | 2 |
| 体外衝撃波結石破砕術 | 37 | 8 | 27 |
| 前立腺針生検 | 67 | 51 | 31 |
▶膀胱癌
痛みがないのに肉眼的な血尿が出たら膀胱癌の疑いがあります。診断には膀胱鏡検査が推奨されます。当院では軟性膀胱鏡を使用し、痛みを低減するように心がけて検査を行っています。
初期治療には経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)を行います。2017年12月に、膀胱癌を光らせて切除する、アミノレブリン酸利用光力学診断(ALA-PDD)併用TURBTが保険適応となりました。この方法により経尿道的手術における膀胱がんの取り残しが少なくなるメリットがあります。当院ではSBIファーマ社の診断装置アラダック®︎を導入しており、ALA-PDD併用TURBTを施行しています。また、膀胱腫瘍の経尿道的切除方法は腫瘍をバラバラにしながら切除する方法が一般的ですが、小さめの腫瘍には一塊で剥離切除する方法(en-block TURBT, TURBOとも呼ばれます)があり、この切除法で切除することで正確な浸潤度診断ができることや、再発率を低減できる可能性が示唆されています。適応症例に対してはen-block TURBTを行ないます。
経尿道的手術により得られた病理組織の診断結果により追加治療の必要性を考慮します。筋層非浸潤性膀胱癌であれば、追加治療として再度の経尿道的手術(セカンドTURBT)や膀胱内薬剤注入治療(BCG膀胱注入または抗癌剤膀胱注入)を行います。筋層以上の浸潤性膀胱癌であれば膀胱全摘除術が標準治療であり、周囲浸潤や遠隔転移などの状態により手術前後に抗癌化学療法を組み合わせる治療が勧められます。
進行性膀胱癌に対しては数年前までは主要な治療法は抗癌化学療法しかありませんでしたが、近年、免疫チェックポイント阻害剤や抗体薬物複合体といった新規薬剤が保険適応となり、治療選択肢の幅が広がりました。当院では最新のガイドラインに準拠しながら、個々の患者さんの状態に合わせて十分に相談して治療法を選択します。
▶腎盂尿管癌
腎盂(腎臓内の尿の集まる部屋)や尿管(腎臓から膀胱までの尿の流れる管)にできる癌が腎盂尿管癌です。病理組織は膀胱癌と同じ尿路上皮癌で、症状も血尿が主な症状であり膀胱癌と近い癌ですが、膀胱と違い尿管の壁が薄いことや発見されにくいことから注意が必要な病気です。主な治療法は手術摘除であり、腎臓から尿管までを摘除する腎尿管全摘除術が標準的な手術です。腎臓から尿管までを摘除するため、手術では腎臓周囲は腹腔鏡手術で行い、尿管周囲は開腹で行います。手術前後に抗癌剤治療を組み合わせることも考慮します。
▶前立腺癌
前立腺癌は男性罹患率1位の癌ですが、国立がん研究センターの報告では5年相対生存率が99.1%と予後の良い悪性疾患です。しかしながら罹患する方が多いうえ、症状が出ることが少なく、進行した状態で見つかることもあるため、早期発見・早期治療が大切と考えます。早期発見に必要なのが血液検査の腫瘍マーカー項目であるPSA検査です。PSA値で異常があればMRIと前立腺針生検検査を行ない確定診断します。前立腺癌があれば全身の状態を検査し、悪性度や進行状態を見極めてから、さまざまな治療の中から状態にあった治療法を選択します。
前立腺癌の主な治療には手術、放射線治療、内分泌治療(ホルモン療法)があり、悪性度の低い微量の前立腺癌ではすぐには治療しない積極的経過観察を選択することも可能です。
限局性前立腺癌では個々の年齢や体力、希望も考慮しながら治療法を選択します。
手術療法は現在ロボット支援手術が主流であり、手術を希望される患者さんにはロボット支援施行可能な施設を紹介させていただいています。
放射線治療は当院の放射線治療科と連携し、強度変調放射線治療(I M R T)を行なっており、前立腺以外に余分な放射線が当たらないようにしながら十分な治療線量を前立腺へ照射します。
転移がある進行前立腺癌に対しては薬剤治療を行います。主に内分泌治療(ホルモン療法)と呼ばれる方法で内服と注射を用いた治療が主流です。近年、新規薬剤が保険適応となり治療成績の改善が期待されています。適応があれば新規薬剤を考慮し、年齢や体力、生活を考慮しながら相談のうえで適した薬剤を選択するようにします。ホルモン療法の効果が低い前立腺癌に対しては抗がん剤治療を行います。
そのほか、状態により放射線治療を組み合わせて治療を行うことも検討します。
▶腎臓癌
腎臓癌は検診や他の病気でたまたま撮影した画像検査で偶然発見されることが多い癌です。多くの場合手術摘除が望ましく、近年では傷口の小さい腹腔鏡下手術が行われています。当院でも積極的に腹腔鏡下手術を行なっています。4cm以下の小径腎癌に対しては癌の部分だけを切除する腎部分切除が推奨され、当院では腹腔鏡下手術を行います。ロボット支援手術の方が手術に有利な場合にはロボット支援手術が施行可能な施設での治療を提案させていただくこともあります。中等度から大きな腎臓癌に対しては腎摘除術が選択され、当院では腹腔鏡下手術を行なっています。さらに大きな腎癌には開腹手術が必要なことがあります。また、転移のある進行腎癌に対しては分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などが保険適応となり治療選択肢が増えています。当院では最新のガイドラインに沿った薬剤選択を基本とし、地域がん診療拠点病院として、新規適応薬剤は速やかに導入し個々の状態に沿って治療を行います。
▶精巣癌
痛みなく精巣が大きくなると精巣癌の可能性があります。特に20代から40代の比較的若年にも生じやすい癌で、進行が早いものが多いため可及的速やかな治療が必要です。治療はまずは手術で腫瘍のある精巣を摘除し、組織型や進行の程度により抗癌剤治療や放射線治療を行います。進行性精巣がんに対する抗癌剤治療中はつらく感じることもあるかもしれませんが、しっかりした治療を行うことで根治することが期待できるため積極的な治療を心がけています。
▶副腎腫瘍
副腎腫瘍の多くは良性腫瘍ですが、血圧や電解質などをコントロールするホルモンを過剰に産生するものがあり、これらに対し摘除手術が行われます。当院では腎臓内分泌代謝内科と連携し、内科での初期治療や詳しい検査による診断ののち、手術治療が必要であれば腹腔鏡下手術を行います。
▶尿路結石
尿路結石は、日本の男性は7人に1人、女性は15人に1人が生涯に罹患する、もはや国民病といっても良いくらいの疾患で、強い疝痛発作が特徴的です。結石のサイズや場所、痛みの強さや尿路感染症の合併など個々の状態によって適した治療が異なります。1cm以下の結石は保存的治療で排石されることもありますが、自然排石されない結石や大きなサイズの結石は、腎機能の悪化や有熱性尿路感染症の原因となるため早めの治療が望ましく、1ヶ月間動かない結石に対しては手術などの治療介入が勧められます。
当院には体外衝撃波結石破砕装置、軟性尿管鏡、細径硬性尿管鏡、細径腎盂鏡、ホルミウム・ヤグレーザー、超音波結石吸引機を備えており、尿路結石に対してさまざまなアプローチによる手術治療が可能です。
▶排尿障害
年齢とともに排尿機能は低下します。高齢化が進み排尿のトラブルを抱える方が増えてきました。
男性では前立腺肥大症が排尿障害の主な原因となる疾患です。前立腺肥大症では、肥大した前立腺が尿道を圧迫することで尿の勢いが低下し、これが長期間続くと膀胱の機能が低下し頻尿も合併することが多くなります。さらに悪化すると排尿後でも尿が出し切れていない状態となり、頻尿で困っている(尿が出過ぎて困る)と思っていたら実は尿が出し切れていないということもあります。最終的には自力で尿が出せない状態となり、腎機能が低下することがあります。初期治療では内服薬による保存的治療を行いますが、膀胱結石の合併、前立腺肥大症からの出血、残尿が多い場合、または希望される場合(内服薬を中止したい、排尿の調子をもっと良くしたいという希望)は経尿道的手術による前立腺腺腫切除を行います。当院では生理食塩水を用いたTURis biporlarシステムを用いて、合併症を少なくしながら腺腫をくりぬいてから裁断する方法で切除し、しっかり尿道を広げる手術法(TUEB)を施行しています。
女性では主に加齢とともに尿失禁や頻尿などの症状でお困りになる方が多くなります。膀胱容量が小さくなることや過敏になるなどの過活動膀胱が原因となることが多いですが、排尿障害が隠れており残尿が多いために頻尿が起こることもあるため、しっかり診察してから状態にあった治療を提案します。内服薬による治療が主になります。また、骨盤内の臓器が下がる骨盤臓器脱が症状の原因となることもあるため婦人科とも協力しながら適した治療を提案いたします。
▶当院における前立腺癌に対する新規アンドロゲン受容体標的薬(ARAT)の有効性及び安全性の検討
詳細はこちら(R4-21 PDF 612KB)をご覧ください。
▶当院における筋層非浸潤性膀胱癌(NMIBC)に対する経尿道的一塊切除(TURBO)の検討
詳細はこちら(R4-20 PDF 596KB)をご覧ください。