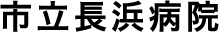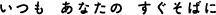心臓血管外科
ご案内 スタッフ紹介 外来担当医表 学会・論文発表 診療実績 診療トピックス
ご案内
| ■診療内容 |
当科では心臓および血管の手術を専門にしており、次のような手術を行っています。
|
|---|---|
| ■施設認定 | 心臓血管外科専門医認定機構認定修練施設(基幹施設) 胸部ステントグラフト実施施設 腹部ステントグラフト実施施設 下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術の実施基準による実施施設 日本心血管インターベンション学会認定研修関連施設 |
| ■診療科の特徴 | いかなる手術においても、安全性を第一におき、皆さまに常に最新の医療を提供できるように心がけております。緊急手術が必要な症例にも24時間体制で対処しております。 |
スタッフ紹介
| 役職等 | 名前 | 資格 |
|---|---|---|
| 責任部長 | 榎本 匡秀 | 心臓血管外科専門医認定機構認定心臓血管外科専門医・修練指導者 日本外科学会専門医 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医 弾性ストッキング・圧迫療法コンダクター 腹部ステントグラフト実施医・指導医 胸部ステントグラフト実施医 経カテーテル大動脈弁置換術(TAVR)実施医 |
| 主任部長 | 長門 久雄 | 心臓血管外科専門医認定機構認定心臓血管外科専門医・修練指導者 日本胸部外科学会指導医・認定医 日本外科学会指導医・専門医・認定医 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医 |
| 部長 | 古根川 靖 | 日本外科学会外科専門医 心臓血管外科専門医認定機構認定心臓血管外科専門医 |
| 副医長 | 松林 優児 | 日本外科学会外科専門医 下肢静脈瘤に対する血管内治療実施基準による実施医 |
| 担当医師 (非常勤) |
洞井 和彦 | 心臓血管外科専門医認定機構認定心臓血管外科専門医・修練指導者 日本外科学会外科専門医 日本外科学会外科専門医 日本外科学会指導医・認定医 日本胸部外科学会認定医 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医・指導医 |
外来医担当表
外来担当医については、下記リンクをご参照ください。
休診、代診のお知らせについては、下記リンクをご参照ください。
学会・論文発表
学会・論文発表につきましては、下記リンクをご参照ください。
診療実績
(単位:件数)
| 手術 | 2023年 (1月~12月) |
2022年 (1月~12月) |
| 虚血性心疾患(冠動脈バイパス術) | 7 | 4 |
| 弁膜症(弁形成術) | 27(7) | 15(10) |
| 心房細動手術(メイズ手術) | 4 | 3 |
| 先天性心疾患 | 0 | 1 |
| 腫瘍など その他の心臓手術 | 2 | 2 |
| 胸部大動脈瘤手術(ステントグラフト) | 26(3) | 21(4) |
| 腹部大動脈瘤手術(ステントグラフト) | 39(20) | 40(19) |
| 閉塞性動脈硬化症など末梢血管手術 | 9 | 12 |
| 静脈瘤手術 | 79 | 98 |
| 透析用シャント手術 | 25 | 53 |
※2022年1月~2023年12月の入院での手術件数を集計しています。
診療トピックス
冠動脈バイパス術とは?
どんな病気に行う手術なの?
心臓の筋肉に酸素と栄養を送る冠動脈という血管が、動脈硬化のため狭くなったりつまったりすると、狭心症といって胸痛発作がおこったり、心筋梗塞といって心臓の一部が動かなくなったりします。これを改善する手術です。
どんな手術?
狭くなったり、つまってしまった冠動脈を迂回するように、新しい別の道(バイパス)を作り、血液の流れを良くします。
どんな血管を使って新しい道を作るの?
胸の中にある内胸動脈がよく使われます。その他、手の橈骨動脈、お腹の中にある胃大網動脈を使ったり、足の静脈を使うこともあります。
手術のとき心臓はどうなっているの?
以前は、人工心肺という装置を使って体全体に血液を流し、心臓の動きを止めて手術をしましたが、最近は、心臓をはじめ、体全体の負担を少なくするために、心臓が動いているままで手術することが多くなりました。
どのくらい入院するの?
手術直後は集中治療室にはいっていただきますが、ふつう術後1~2週間くらいで退院できます。
【本院の特徴】
人工心肺装置を使用しないため、身体にやさしい手術になり腎臓の悪い方や、腫瘍(ガン)を合併しておられる方でも手術できる機会が大きく広がリ、安全に手術を受けていただけるようになっております。
弁膜症手術について
弁膜症とは?
心臓には4つの部屋があり、その中を血液が一方向に流れるように弁があって、逆流を防いでいます。これらの弁の働きが悪くなると、血液が流れにくくなったり(狭窄症)、逆流したり(閉鎖不全症、逆流症)して、心臓に負担がかかってきます。
放っておくとどうなるの?
狭窄や閉鎖不全が軽い間は無症状ですが、そのうちに心臓や肺に負担がかかるようになり、息切れ、むくみなどの心不全状態となって、肺うっ血、突然死といった生命にかかわる状態に進行します。自覚症状が出だしたときはかなり病気が進んでいるということです。
手術しないと治らないの?
心臓の働きが悪くなるのをある程度は薬で抑えることができますが、根本的な治療は手術以外ありません。手術時期が遅くなると心臓の働きが悪くなりすぎて、手術をしても回復が難しいことがあります。早めの手術が良い結果につながります。
どんな手術なの?
人工心肺という装置を使って、体に血液を送りながら、心臓の動きを止めて弁を治します。自分の弁をできるだけ残して、弁の働きをとりもどすように修繕したり(形成術)、人工弁に取り替えたり(置換術)します。
人工弁をいれるとどんな不便が?
人工弁には、金属でできた機械弁と、動物の弁を加工した生体弁があります。機械弁は耐久性に優れますが、血栓予防のため生涯にわたりずっとワーファリンという薬をのみ続けなければいけません。生体弁はその必要はありませんが耐久性に限界があります。その選択は一般的に患者様の年齢を参考にしています。最近の生体弁はかなり優れたものが開発されていて、以前に比べてかなり安心できるものとなっています。人工弁をいれていても、MRIなどの磁気を利用した検査には影響ありません。
手術は怖い?
長く放置しておいたため心不全がかなり進んでしまった場合は手術の危険性が高くなりますが、ほとんどの手術は良好な結果がでています。生命にかかわる危険性は1~2ハ゜ーセントくらいです。入院期間はふつう手術後1~2週間くらいで退院できます。ご高齢の方(80歳以上)でもとくにかわりはありません。
大動脈瘤について
高齢社会で増えてきている大動脈瘤という重大な病気があります。
大動脈瘤とは?
大動脈というのは、心臓から体全体に血液を運ぶ太い血管で、体の中心(背骨の前)を走っており、それから枝分かれして体のすみずみまで血液を送っているのです。この太い血管が、まるで風船がふくらむようにコフ゛状にふくらんだ状態を大動脈瘤といいます。原因は、高齢化に伴う動脈硬化などにより血管の壁が弱くなり、そこに高血圧が加わってふくらんでくるものがいちばん多く、まれに外傷、感染、生まれつきの血管異常などが原因のこともあります。瘤ができる場所は様々ですが、胸部と腹部に分かれ、腹部のほうが高い比率で発生します。
放っておくとどうなるの?
破裂して命にかかわる状態になります。
どうしたら見つかるの?
この病気が怖いのは自覚症状がほとんどないために、破裂してはじめてわかるようなことでは手遅れになってしまうことです。かなり大きくなるとまれに胸、背中、腹に鈍い痛みや不快感、また胸部瘤の場合には声がかすれるなどの症状がありますが、大半は他の病気でCTや超音波の検査を受けた時に偶然見つかる事がほとんどです。破裂直前に強烈な痛みがあったり、腹部瘤の場合は、おへそのあたりにト゛ント゛ンと脈を打つしこりに気がつくこともあります。
どんな治療をするの?
外科的に手術するしか方法はなく、薬で瘤が小さくなる事はありません。手術では、ふくらんだ血管を人工血管(合成繊維でできています)に取り換えます。胸やお腹を切ることのないステントグラフト手術もあり、最適な方法を相談のうえ選択します。
手術の危険性は?
破裂する前の元気な状態で手術をすれば、胸部で5%くらい、腹部では1%以下といわれていますが、緊急手術では30~50%の死亡率になります。
当科から一言
動脈瘤があるといわれている方、まだ大きくないので大丈夫と思っていたり、手術が怖いと言って手術の決心がつかない方はおられませんか?この大動脈瘤というのはけっして小さくはなりません。手術は瘤が小さいうちにするほうが、危険度も合併症の発生率も低く、瘤が大きくなるまで待つというのは間違いです。待っていることによりそれだけ手術する時の年齢も高くなり、手術の難しさも確実に高くなります。また、破裂する確率も上がり、一旦破裂すればいちかばちかの手術になってしまいます。手がつけられない状態になる事も考えられます。もういい歳だから手術は受けたくないとお考えの方もおられると思います。しかし、実際に破裂してしまうとご本人は判断ができなくなり、ご家族の方があわてられます。緊急手術ができればすることになりますが、命にかかわり、助かっても後遺症が出るという事が多くなりその後の介護が大変です。最近では80歳を超えている方も珍しくありません。特に腹部大動脈瘤の方は年齢に関係なく手術可能と考えております。胸部瘤に関しては手術の危険性が高くなるため、広い視野で検討したうえで手術が可能かどうかを相談させていただきます。
大動脈瘤があると一度でも言われた方、また、高血圧でおなかにしこりがあるという方は受診してください。
大動脈解離(解離性大動脈瘤)について
大動脈解離ってどんな病気?
心臓から出ている体の中で一番太い血管の壁に亀裂が入り、壁がはがれてゆく病気です。原因はほとんどが高血圧で、まれに外傷が原因となったり、先天性の体質的なこともあります。高齢者に多い病気ですが、若くても発症します。
どんな症状?
胸や背中の強烈な痛みをきたし、血管が裂ける位置によって痛みが移動します。意識をなくすこともあり、そのまま亡くなられる方もあります。血管の裂けかたによっては、緊急処置ができなければ48時間以内に50%くらい、1週間以内に70%の方が亡くなられるとも言われています。
治療方法は?
即刻手術をしなければいけない場合と、血圧を下げてしばらくの間様子を見ることができる場合とがありますが、緊急手術が多いようです。
どんな手術?
解離の原因となった裂け目のある血管を人工血管に取り替える手術を行います。その際、人工心肺という機械を使い体温を下げるのが一般的です。取り替える血管の長さや部位にもよりますが、手術は比較的長時間を要し、出血を止める操作に全力を尽くします。難しい手術だけに合併症や後遺症の発生率も高くなります。しかし、急性の解離を放置した場合のほうが結果が不良と言われています。手術の死亡率は約10%くらいです。入院期間は順調に経過した場合1ヶ月くらいでしょう。
高血圧と言われている方は、突然の激しい胸背部痛に注意してください。
閉塞性動脈硬化症について
動脈硬化により血管の壁が厚くなって血液の流れる通路が狭くなり、血流が不足するため筋肉に酸素が充分行き渡らなくなる病気です。
どんな症状がでるの?
軽い場合には足の冷感やしびれがあります。病気が進んでくると、歩いたり走ったりした時に足が痛くなり、休憩をとると痛みがとれてまた歩けるようになります。これを間歇性跛行と言います。さらに重症になると、安静時でも足が痛み、時には壊疽と言って足の先が変色し腐ってくるようになります。
なぜこんな病気になるの?
高度の動脈硬化で血管がつまってくるのですが、その要因として、高血圧、高コレステロール血症、喫煙、肥満、糖尿病、加齢があります。これらは狭心症、動脈瘤などの原因ともなるので、狭心症や心筋梗塞、動脈瘤と診断されている患者様にはかなり高い頻度でこの病気が合併しているとされています。
自然に治らないの?
一旦狭くなったり詰まってしまった血管はそのままでは元に戻りませんが、人間の体は、なんとか悪くならないように別の血管を作ろうとします。血液の流れが悪いところをハ゛イハ゜スして足先に血液を流そうと頑張ります。これを側副血行路と言います。しかし、血流量が充分ではなく、進行すればやはり壊死を引き起こします。タバコはかなり病気を悪くします。その証拠に、禁煙することで、歩行距離が延長します。
どうしたら見つけられるの?
足の動脈をさわってみます。足の付け根(大腿動脈)、膝の裏側(膝窩動脈)、足の甲(足背動脈)、内くるぶしの下(後脛骨動脈)で脈が触れるかどうかがホ゜イントです。しかし、どの程度であるか、手術が必要かどうかはさらに検査しなくてはなりません。手足の血圧を同時にはかったり、血管のレントケ゛ン写真(動脈造影)をとってみる必要があります。
どんな治療があるの?
内服薬で不充分なときには、風船治療や外科的血行再建術をします。症状がひどい場合は手術になる事が多く、人工血管移植などで症状が著しく改善します。病気が進行して壊死になってしまった場合は切断手術をせざるをえません。
当科から一言
足の痛みを訴える方は多いのですが、血管(血流)が原因の病気と考える患者様は少なく、まず整形外科の門をたたく方が多いようです。背骨や腰の病気のように整形外科関連のものもありますが、血管外科の受診もされてはいかがでしょうか?血行再建術の後でタバコをすうことは手術結果を悪くしますので、厳に慎んでいただきたく思います。
下肢静脈瘤とは?
下肢の静脈がるいるいと盛り上がってくる病気です。どちらかと言えば女性に多い病気ですが、立ち仕事が多い人にみられます。女性では出産をきっかけにして起こってくることが多い病気です。
どんな症状?
初期は美容的な問題だけで症状はありませんが、次第に足が重くなってきたり、膨らんだ静脈の中に血液のかたまりができて、痛みや熱をもったりすることがあります。時には湿疹や皮膚炎をもひきおこし、色素沈着をきたします。
どんな治療があるの?
下肢静脈瘤の治療には、弾性ストッキングによる圧迫療法、硬化剤を注入する硬化療法などの治療法と、静脈瘤を切り除いたりする手術、カテーテルで高周波、レーザー光で静脈瘤を焼灼する手術などがあります。どの治療法も有効で、その適応も踏まえて、外来で説明させていただきます。昨今、患者様へのストレス、負担軽減のために、下肢静脈瘤治療は低侵襲化が進みました。今回、2020年4月からは血管内塞栓術が従来の手術に加えて、保険認可されました。より低侵襲な治療法であり、当科も2020年9月には導入開始いたします。
内シャント作成とは?
手の動脈と静脈をつなぎあわせる手術です。
何のために?
透析治療の際に血液を出し入れするための太めの針を刺すことができるように、静脈を太くしてやります。透析は長期にわたって必要なので、血液の流れが少なくなった時にはシャントを作り変える事もあります。