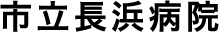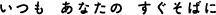歯科・歯科口腔外科
ご案内 スタッフ紹介 外来担当医表 届出を行っている施設基準等のご案内 学会・論文発表
ご案内
| ■診療内容 | 当科では、主に顎口腔領域の炎症・外傷・腫瘍・粘膜疾患・顎関節疾患などの歯科口腔外科疾患を対象に診療を行っています。 2000年から湖北地域のしょうがい者歯科医療の一端を担うため、しょうがい者歯科専門外来を開始しています。現在、毎月第1、3水曜日の14:30~16:30に診療を行っています。また、超高齢社会のニーズに応えるべく、多科・多職種と連携を取りながら摂食嚥下機能の評価および機能訓練など行っています。 一方、当院は2005年に厚生労働省から地域がん診療連携拠点病院に指定されています。近年、がん治療などにおける周術期口腔機能管理の重要性が認識されるようになり、当科においてもがん患者さんだけでなく、あらゆる疾病を持つ患者さんの口腔機能管理を行っています。 |
|---|---|
| ■施設認定 | ・日本口腔外科学会認定准研修施設 |
| ■患者さんへ | 当科では口腔領域の外科的疾患を中心に取り扱っております。 歯科治療に関しては、全身疾患などのため歯科医院での治療が困難な場合を除いて、原則、近隣の歯科医院への受診をお願いしております。 |
スタッフ紹介
| 役職等 | 名前 | 資格 |
|---|---|---|
| 特任部長 (嘱託医) |
近藤 定彦 | 日本口腔外科学会指導医 厚生労働省歯科医師臨床研修指導歯科医 |
| 副医長 | 田代 千紘 | (休診中) |
| 担当医師 (非常勤) |
不定期 | |
| 担当医師 (非常勤) |
不定期 |
外来担当医表
外来担当医については、下記リンクをご参照ください。
休診、代診のお知らせについては、下記リンクをご参照ください。
届出を行っている施設基準等のご案内
<感染防止対策について>
口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者さんごとの器具の交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなどして院内感染防止対策を行っています。また、安心して治療を受けていただくために、口腔外吸引装置を設置し、器械に使用する水やエアーには除菌フィルターを設置しています。
(当院歯科口腔外科は厚生労働大臣が定める施設基準に適合し「地域歯科診療支援病院歯科初診料」「歯科外来診療感染対策加算3」を算定しています)
<医療安全管理対策について>
安全で良質な歯科医療を提供し、患者さんに安心して治療を受けていただくために、医療安全に関する指針を整備して医療安全対策を行っています。また、急変時の搬送先として当院救急センターと連携し、緊急時の体制を整えています。
(当院歯科口腔外科は厚生労働大臣が定める施設基準に適合し「歯科外来診療医療安全対策加算2」を算定しています)
<歯科技工について>
良質な歯科技工物を製作し、かつ迅速に有床義歯の修理および床裏装がおこなえるように常勤「歯科技工士」を配置しています。また、院内技工室を整備し、製作に必要な歯科技工機器・材料の適正な管理に努めています。
(当院歯科口腔外科は厚生労働大臣が定める施設基準に適合し「有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2」「歯科技工士連携加算1」を算定しています)
<クラウン・ブリッジ等の維持管理について>
保険適応で治療の際に硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠、レジン前装チタン冠、チタン冠、ブリッジ(全ての支台をインレーとするブリッジを除く)を装着された場合、治療費に厚生労働省の定めによるクラウン・ブリッジ維持管理料を頂いております。もしも2年以内に破損等があり、新しく作りなおすときは、その部分の検査費、製作費、装着費は無料となります。ただし、初診料やその他の治療費は除き、6歳以下の乳幼児や在宅治療は対象外です。
(当院歯科口腔外科は厚生労働大臣が定める施設基準に適合し「クラウン・ブリッジ維持管理料」を算定しています)
<有床義歯の取り扱いについて>
新しい義歯(取り外しのできる入れ歯)を新しく作った後、6ヶ月間は新たに作り直すことができません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です。
学会・論文発表
学会・論文発表につきましては、下記リンクをご参照ください。