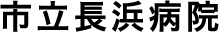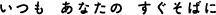腎臓代謝内科
ご案内 スタッフ紹介 外来担当医表 学会・論文発表 診療実績 診療トピックス
ご案内
| ■診療内容 | 当科は湖北地域で唯一の腎臓内科であり、湖北地域のみならず広く患者様を受け入れております。軽症のタンパク尿や血尿、軽度の腎機能障害から重症の急性腎不全・高度の腎不全までお気軽にご相談いただければ幸いです。 |
|---|---|
| ■施設認定 |
日本内科学会認定医制度教育病院 |
| ■診療科の特徴 |
特に慢性腎臓病に対しては2014年9月から「慢性腎臓病1週間教育入院」を立ち上げ、すでに様々な施設から患者様をご紹介いただいております。また慢性腎臓病(CKD)の地域連携パスを活かして腎疾患の地域医療を充実させるべく進めております。 末期腎不全に対しては、従来の血液透析に加え2014年11月から腹膜透析も導入いたしました。より患者様のニーズに合った治療法を選択する事ができるようになりました。透析患者に対して各診療科がアクティブに行う診療にも専門知識を活かして対応しております。 糖尿病においても専門的な治療を行っております。GLP-1受容体作動薬をはじめ日進月歩する糖尿病治療薬を駆使して診療を進めております。特に腎障害を合併した糖尿病治療は当科の特徴を活かせる分野であると自信を持って取り組んでおります。 |
スタッフ紹介
| 役職等 | 名前 | 資格 |
|---|---|---|
| 責任部長 (診療局長) |
森田 善方 | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本透析医学会透析専門医・指導医 日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医 日本腎臓学会腎臓専門医・指導医 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門研修指導医 日本医師会認定産業医 |
| 部長 | 潮 正輝 | 日本内科学会認定内科医 日本糖尿病学会専門医 日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医 日本人間ドック・予防医療学会認定医 |
| 部長 | 上田 久巳 | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本腎臓学会腎臓専門医 日本循環器学会循環器専門医 日本透析医学会透析専門医 VAIVT認定専門医 VAIVT血管内治療医 VA血管内治療認定医 |
| 部長 | 島本 綾子 | 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本腎臓学会腎臓専門医 |
| 副医長 | 岡島 良奈 | |
| 担当医師 (専攻医) |
村田 航 |
外来担当医表
外来担当医については、下記リンクをご参照ください。
休診、代診のお知らせについては、下記リンクをご参照ください。
学会・論文発表
学会・論文発表につきましては、下記リンクをご参照ください。
診療実績
診療実績(単位:件数)
| 2023年 (1月~12月) |
2022年 (1月~12月) |
2021年 (1月~12月) |
|
| 腎生検数 | 104 | 90 | 115 |
| 透析新規導入数 | 31 | 54 | 39 |
診療トピックス
糖尿病について
血液中の糖を細胞内に取り込む働きをしているインスリンというホルモンの作用が絶対的あるいは相対的に不足し、血糖(血液中の糖の濃度)が高く維持される病気です。厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、糖尿病とその予備群の方が1997年では980万人だったものが、10年後の2007年には2210万人に急増しています。
糖尿病の症状として、口渇(喉の渇き)・多飲(多量の水分摂取)・多尿(尿量の増加)がありますが、ほとんど無症状の場合も多く、重大な合併症が出てから初めて気付かれることも稀ではありません。合併症には脳梗塞・心筋梗塞や足の血管が詰まる閉塞性動脈硬化症といった大きな血管が侵されるものから、最悪の場合失明に至る網膜症・透析が必要となる腎症・痺れや感覚鈍麻の原因となる神経しょうがいといった小さな血管が侵されるものまであり、いずれも命や生活の質に大きく関わるものばかりです。現在、治療が必要であるにもかかわらず、治療を受けていない方が未だに50%もおられると言われています。糖尿病や合併症が進行してしまうと、治療を始めても進行を遅らせるのが精一杯という状態になりかねません。早期に治療を開始できれば、重大な合併症の予防につながりますし、定期的な健康診断・早めの受診・合併症の精査・治療をお奨めします。
腎不全について
腎臓は尿をつくる臓器で、血液中の老廃物(ゴミ)や不要な水分を尿として体外に排出させることで、体内のバランスを整えています。腎不全とは、様々な原因で腎臓が十分に働かなくなった状態で、正常な尿がつくれなくなり、その結果、体内に老廃物や水分が蓄積し、様々な症状を引き起こします。老廃物が蓄積すると、倦怠感・食欲低下・吐き気・嘔吐・意識しょうがい・皮膚の痒みといった尿毒症症状が出現しますし、水分が蓄積すると、全身のむくみ・胸に水が溜まることによる呼吸困難・高血圧といった症状が出現します。これ以外にも、腎臓は血液をつくる司令塔の役割を果たしていたり、骨の代謝に関わっているため、貧血が進んだり、骨がもろくなったりします。
一般に腎臓の機能を知る指標には、血清クレアチニン(正常0.7~1.3mg/dl)、血中尿素窒素(BUN)(正常6~21mg/dl)があります。これらは、尿中に排出される老廃物の一種で、腎機能が低下すると、体内に蓄積して、値が上昇します。ただし、これらの指標は、腎機能が相当悪くなって初めて上昇し始めるので、少しでも上昇があれば、注意が必要です。腎不全の原因や合併症や年齢により異なりますが、一般的に血清クレアチニンが8mg/dl以上(腎機能が正常の5~10%程度)になると、腎臓の機能を人工的に代行する腎代替療法が必要になります。
腎代替療法には、以下の3通りがあります。
(1)血液透析
現在最も一般的に行われている方法で、当院では約80名の患者様が週2~3回、1回3~5時間行っておられます。血液を体外に出し、ダイアライザーという透析器を通すことによって、血液中の老廃物・余分な水分を除去し、体に不足している物質を補い血液をきれいにして、再び体内に戻す方法です。この治療を行うには、血液を多量に送る太い静脈が必要になるので、腕の動脈と静脈をつなぎ合わせ、動脈の豊富な血流を静脈に流す手術が必要です(内シャント造設術)。手術後、シャントが使用できるまでに、数週間から数か月かかるので、腎機能が低下し、近いうちに透析が必要となると、事前に手術することが推奨されます。
(2)腹膜透析
全国の透析患者の6~10%が腹膜透析を行っております。腹膜に囲まれた腹腔内に透析液を注入し、一定時間(5~8時間)貯留させると、腹膜が透析膜の役割を果たし、血液中の老廃物や余分な水分が腹腔内の透析液へ移行します。これを体外に出すことで、血液をきれいにする方法です。透析液の貯留・排出を1日あたり1~5回繰り返します。この治療を行うには、腹腔内に透析液を出し入れする管(腹腔内カテーテル)を腹部に留置する手術が必要です。血液透析と比べると、体への負担が少なく、食事制限もゆるやかで、家庭や職場など社会生活の中で自分のスタイルに合わせて、患者様自身が行う透析です。また、特に異常がなければ月に2回程度の通院で済みます。ただし、長期に行うと腹膜の機能がおとろえて老廃物や水分の移行が悪くなったり、硬化性腹膜炎という腸が硬く癒着する合併症を引き起こすことがあるため、数年~十数年後には他の治療に移行する必要があります。
(3)腎移植
ドナーの健康な腎臓を移植する治療です。健康な腎臓が1個あれば、尿に老廃物や余分な水分を十分に排出できるので、腎不全の原因にもよりますが、健康な人と同様の日常生活が送れるようになります。ただし、ドナー不足のため移植できる件数は限られており、また、拒絶反応を抑えるため、免疫を抑える薬を飲み続ける必要があります。
当科では心臓血管外科医・泌尿器科医と協力し、1を中心に行っております。いずれの方法にも長所・短所があり、また患者様の状態・合併症・勤務や居住地の条件などによっても適応が変わってきますので、患者様およびご家族とよく話し合って決めることが大切です。
慢性腎臓病(CKD)について
慢性腎臓病(CKD)とは、
1).尿蛋白や画像所見、血清クレアチニンの上昇など、腎しょうがいの存在が明らか
2).腎機能が正常の約60%以下
のいずれか、あるいは両方が3か月以上持続する状態のことです。
最近の大規模研究により、「腎機能が低下していること」そのものが、腎不全に陥る危険性だけでなく、糖尿病・高血圧・高脂血症などと同じように、心筋梗塞などの重大な危険因子であることが判明し、CKDが注目されるようになりました。定期的な健康診断にてCKDの疑いがある場合には、早期に専門病院を受診し、腎機能低下の進行を抑制するだけではなく、心筋梗塞などの予防対策をとることが望まれます。