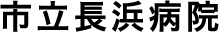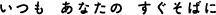理念・方針・指針等

理念 基本方針 患者権利章典 子どもの患者さんと家族の権利 個人情報の取り扱い 宗教上の理由等による輸血拒否に対する当院の対応 適切な意思決定支援に関する指針
理念
地域住民の健康を守るため、「人中心の医療」
を発展させ、地域完結型の医療を推進します。
基本方針
- 患者の権利、尊厳を重視した医療を実践します。
- 地域の医療関係者との連携を深め、地域医療の発展のためにつくします。
- 高度で良質な医療水準を確保し、安全で信頼される医療を進めます。
- 快適な療養環境の整備と、質の高いケアに努めます。
- 医学研究活動を推進し、優れた医療人を育成します。
- 職員が互いに尊重、協力してチーム医療を実現します。
- 職員が元気で働きがいのある職場づくりに努めます。
患者権利章典
私たちは、「人中心の医療」の理念のもと、患者さんの権利を大切にし、守ります。
また、患者さんとの相互の信頼と協力関係にもとづき、患者さんの主体的な参加のもとで医療を推進します。
ここに、私たちは、市民の生命と健康を守るため「患者権利章典」を制定し、患者さんの健康づくり、治療の実践を支援します。
- 個人の尊重
だれもが一人の人間として、その人格や価値観などを尊重されたもとで、医療を受けることができます。 - 適切な医療
だれでも、どのような病気にかかった場合でも、適切な医療を公平に受けることができます。 - 知る権利
病気、検査、治療、見通し、危険性など、自らの診療に関する十分な説明と情報を得ることができます。 - 決める権利
十分に理解し納得した上で、検査や治療などを、自らの意思で選択し決定することができます。 - セカンドオピニオンを求める権利
主治医以外の医師に意見(セカンドオピニオン)を求める権利を尊重します。 - プライバシーの保護
診療の過程で得られた個人情報については、関係法令、条例および院内規程に従い保護され、また院内において私的な生活を可能なかぎり他人にさらされず、乱されないで過ごすことができます。
(患者さん、家族の皆様へのお願い)
適切な医療を行うために、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に伝えていただくとともに、他の患者さんの医療や、職員による医療提供に支障を与えないようご配慮をお願いします。
子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんと家族(かぞく)の権利(けんり)
私(わたし)たちは、「人(ひと)中心(ちゅうしん)の医療(いりょう)」の理念(りねん)のもと、子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんとご家族(かぞく)の権利(けんり)を大切(たいせつ)にします。
また、子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんやご家族(かぞく)との相互(そうご)の信頼(しんらい)と協力(きょうりょく)関係(かんけい)に基(もと)づき、子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんとご家族(かぞく)の主体的(しゅたいてき)な参加(さんか)のもとで医療(いりょう)を推進(すいしん)します。
ここに、私(わたし)たちは、子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんの生命(いのち)と健康(けんこう)を守(まも)るため「患者(かんじゃ)権利(けんり)章典(しょうてん)」をもとに、子(こ)どもの患者(かんじゃ)さんの健康(けんこう)づくり、治療(ちりょう)の実践(じっせん)を支援(しえん)します。
- 個人(こじん)の尊重(そんちょう)
こどもたちはだれもが一人(ひとり)の人間(にんげん)として、その気持(きも)ちや考(かんが)え方(かた)を大切(たいせつ)にした医療(いりょう)を受(う)けることができます。 - 適切(てきせつ)な医療(いりょう)
こどもたちはだれでも、どのような病気(びょうき)にかかった場合(ばあい)でも、その人(ひと)に合(あ)った医療(いりょう)を公平(こうへい)に受(う)けることができます。 - 知(し)る権利(けんり)
病気(びょうき)、検査(けんさ)、治療(ちりょう)、危険性(きけんせい)、今後(こんご)のことなど、こどもたち自身(じしん)の診療(しんりょう)に関(かん)してこどもたちや家族(かぞく)が分(わ)かりやすい方法(ほうほう)で十分(じゅうぶん)な説明(せつめい)を聞(き)いて知(し)ることができます。 - 決(き)める権利(けんり)
検査(けんさ)や治療(ちりょう)の方法(ほうほう)などについて、よくわかった上(うえ)で、こどもたちや家族(かぞく)の考(かんが)えや気持(きも)ちで選(えら)んで決(き)めることができます。 - セカンドオピニオン(せかんどおぴにおん)を受(う)ける権利(けんり)
こどもたちと家族(かぞく)は、違(ちが)う病院(びょういん)の医師(いし)に考(かんが)えを聞(き)くことができます。 - プライバシー(ぷらいばしー)の保護(ほご)
こどもたちと家族(かぞく)は、秘密(ひみつ)にしたいことが守(まも)られます。 - 保育(ほいく)や教育(きょういく)を受(う)ける権利(けんり)
こどもたちは、年齢(ねんれい)に合(あ)った遊(あそ)びや勉強(べんきょう)をすることができます。
個人情報の取扱い
当院では、個人情報の取り扱いについて、「個人情報の保護に関する法律」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に基づき、患者様の治療および公益上等特に必要とする目的のために、下記のとおり個人情報を管理、利用させていただいております。今後も引き続き、個人情報の保護に努めてまいりますので、皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いします。
平成17年4月1日制定
平成29年5月1日改定
令和5年4月1日改訂
院長
医療の提供に必要な個人情報の利用(目的利用)について
◎院内での個人情報の管理について
- 医療の提供のために、診療録、処方箋などの各種指示書、エックス線写真、紹介状・伝票等(以下「診療録等」といいます。)に、個人情報を記載するとともに、コンピュータシステムにデータ入力・保存して管理利用します。
- 診療録等は、関係法令および院内規程に基づき管理保管します。
- 医療・介護・労災、公費負担医療に関する事務や病棟管理・会計・経理・医療安全対策・医療安全事務・院内感染防止対策、患者様サービス向上活動に、個人情報を利用します。
- 円滑に受診いただけますよう、コンピュータシステム等を利用して、院内各部署間の情報の共有を行います。
◎他の事業者や患者様本人以外への情報提供について
- 治療やお世話を行う上で、他の病院、診療所、施設、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者との円滑な連携のために個人情報を利用します。
- 他の医療機関等から患者様への医療の提供のために照会があった場合には回答いたします。
- より適切な診療を行う上で、外部の医師等の意見・助言が必要な場合に情報の収集あるいは情報の提供を行います。
- 在宅医療や検査業務の委託などにおいて、安全・確実な医療の提供のために個人情報を利用します。
- ご家族への病状説明に利用します。
- 医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務において事務の委託や、審査支払機関へのレセプト提出、同機関への照会及び照会に対する回答、保険者への照会及び照会に対する回答、公費負担医療に関する行政機関などへのレセプトの提出や照会への回答に個人情報を利用します。
- 健康保険組合、事業者等からの委託を受けて健康診査等を行った場合には、必要に応じて、健康保険組合、事業者等へその結果を通知します。
- 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社、弁護士等への相談または届出に個人情報を利用します。
個人情報の目的外利用について
◎院内での個人情報の利用について
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料として利用させていただきます。
- 当院は、医師、看護師、薬剤師、医療技術職、救急救命士等の研修教育病院であり、院内で行われる診療研修、学生実習、症例研究の際に利用する場合があります。
◎他の事業者等への情報提供について
- 当院の管理運営業務のうち、国、県などの外部監査機関へ情報を提供する場合があります。
◎学会発表や学術誌発表などの研究に関して
- 医学、医療の進歩のために匿名化したうえで利用させていただくことがあります。この際、事例の内容から十分な匿名化が困難な場合は、その利用については、患者様の同意を得ます。
個人情報の第三者提供について
当院は個人情報を適切に管理し、あらかじめ患者様の同意を得ることなく第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
- 法令や条例に基づく場合(例:医療法に基づく立入検査、児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待に係る通告など)
- 人の生命、身体または財産保護のために必要な場合であって、患者様の同意を得ることが困難な場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成のために特に必要な場合であって、患者様の同意を得ることが困難な場合
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、患者様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき
患者様の同意について
◎個人情報の管理利用への同意、留保について
- 患者様が個人情報の管理利用について、同意しがたいものがある場合は、その旨お申し出ください。なお、患者様がこの意思表示をされない場合は、ここに掲載しております個人情報の管理利用にご同意をいただいたものとします。
- 個人情報の管理利用への同意および留保は、患者様からの申し出によりいつでも変更することが可能です。
診療録の開示について
◎診療録の開示について
- 患者様ご本人による診療録の開示請求があった場合、個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規程に基づき、診療録の開示を行っております。詳しくは医事課までお問い合わせ下さい。
ご相談窓口について
ご相談等につきましては、ご遠慮なく次のところヘお申し付けください。
(ご相談窓口)
| 患者様等からの 医療安全に関す る相談 |
患者医療安全相談窓口 ・窓口設置場所:医療安全管理室 ・受付時間:平日の8:30から17:15まで(外来休診日を除く) |
| 情報開示について | 市立長浜病院医事課 電話番号:0749-68-2300(代表) ・受付時間:平日の8:30から17:15(外来休診日を除く) |
| 個人情報保護全 般について |
長浜市役所 総務部総務課 電話番号 :0749-65-6503 |
宗教上の理由等による輸血拒否に対する当院の対応
当院では、宗教上の理由等による輸血拒否に対しては、相対的無輸血の基本方針に則り、輸血をしない最大限の努力をいたしますが、生命に危機が差し迫った場合は輸血する場合がありますので、何卒ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
基本方針
- 輸血を行う可能性がない検査および治療に関しては、すべての患者さんに対して本人にとって最善の診療をいたします。
- 輸血を必要とするような出血の可能性が予想される検査および処置、手術、分娩などの治療を行う場合は、輸血を行わないためのできる限りの努力をいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険を回避できる可能性があると判断した場合には輸血を行います。この場合、輸血同意書が得られなくても輸血を行います。
- 自己決定が可能な患者さんや、患者さんの保護者、または代理人の方に対しては、当院の方針を十分に説明し、理解を得るよう努力いたしますが、どうしても同意を得ることができない場合は他院での治療をお勧めいたします。
相対的無輸血
患者さんの意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない事態に至ったときには輸血をするという立場・考え方
適切な意思決定支援に関する指針
人生の最終段階を迎えた本人及び家族等と医師をはじめとする医療ケアチーム(医療ケアチームとは、主治医、責任部長、看護師、医療相談員、介護従事者等の医療従事者、及び緩和ケアチーム、認知症ケアチーム)が、最善の医療とケアを作り上げるプロセスを示すために、このガイドラインを策定する。
(厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする)
1. 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
(1)医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。
また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。
さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等、信頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることも重要である。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。
(2)人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
(3)医療ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。
(4)生命を短縮させる意図を持つ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。
2. 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き
人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は次によるものとする。
(1)本人の意思の確認ができる場合
1)方針決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされることが必要である。
その上で、本人と医療ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療ケアチームとして方針の決定を行う。
2)時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援が行われることが必要である。この際、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いが繰り返し行われることも必要である。
3)このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(2)本人の意思が確認できない場合
本人の意思が確認できない場合には次のような手順により、医療ケアチームの中で慎重な判断を行う必要がある。
1)家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の治療方針をとることを基本とする
2)家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人にかわる者として家族等と十分話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
3)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。
4)このプロセスに沿って話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。
(3)臨床倫理専門部会の開催:多職種及び複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、治療方針の決定に際し、
1)医療ケアチームの中で、心身の状態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合
2)本人と医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容につい合意が得られない場合
3)家族等の中で意見がまとまらない場合や医療ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケア内容について合意が得られない場合等については、臨床倫理専門部会に倫理審議申請を行う。臨床倫理専門部会は、治療方針等についての検討及び助言を行い、合意形成に至る努力をする。
(4)認知症等で自らが意思決定することが困難な患者の意思決定支援
障がい者や認知症等で患者自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、家族及び関係者、医療・ケアチームが関与しながら、できる限り本人の意見を尊重した意思決定を支援する。
(5)身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しながら、厚生労働省「身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
3. 医療処置(蘇生処置を含む)に関する確認書及び救命不可能と判断された場合の医療処置(蘇生処置を含む)に関する確認書
この確認書は本人にとって、その時点で最もふさわしい医療・ケアを本人あるいは家族等と共に考え、緩和的アプローチを含めて提供することを意味する。本人、家族等には、十分な説明と意思確認を行い、必要に応じて書面に必要事項を記入してもらい、担当医はこれをカルテに保存する。
補足:医療処置(蘇生処置を含む)に関する確認書及び救命不可能と判断された場合の医療処置(蘇生処置を含む)に関する確認書の解説
蘇生不要指示・DNAR(Do Not Attempt Resuscitation) 指示は日常的に多くの病院で出されている。しかし、そのとらえ方は医療者個人個人で異なっており、DNAR指示によって心肺蘇生(CPR)以外の他の治療に対しても消極的になり、生命維持治療も制限されてしまい、実質的に延命治療の差し控え・中止となっている場合さえある。そこで、CPR以外の他の医療処置内容についても、具体的に十分な考慮が必要であるという趣旨の基にこの確認書を使用する。
なお、本人が別の医療機関や介護施設に移る場合や本人の病状が変化した場合などには、その内容を再評価するべきである。
記録:人生の最終段階における診療記録記載事項
1. 医学的な検討とその説明
①人生の最終段階であることを記載する。
②説明の対象が本人の場合、本人の意思、またはリビングウィル(不治の病の場合の尊厳死希望、延命治療の拒否を表明すること)の有無を記載する。
③本人が人生の最終段階であることについて、本人あるいは家族等に説明した内容を記載する。
④説明に際して、本人あるいは家族等による理解や受容の状態を記載する。
2. 人生の最終段階における対応について
①本人の意思(またはリビングウィル)の内容を記載する
②本人が意思を表明できない場合、家族等による本人の推定意思を記載する。
③家族等の意思を記載する。
④本人にとって、最善の治療方針について検討事項を記載する。
⑤医療ケアチームのメンバーを記載する。
3. 状況及び対応が変化した場合、その変更について記載する。
(参考)
・人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン
厚生労働省 平成30年3月改訂
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン
厚生労働省 令和元年5月
・身寄りがない人の入院および医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
厚生労働省 平成30年6月
平成30年9月制定
令和6年10月16日一部改正
市立長浜病院
適切な意思決定支援に関する指針(令和6年10月16日一部改正)(PDF 200KB)